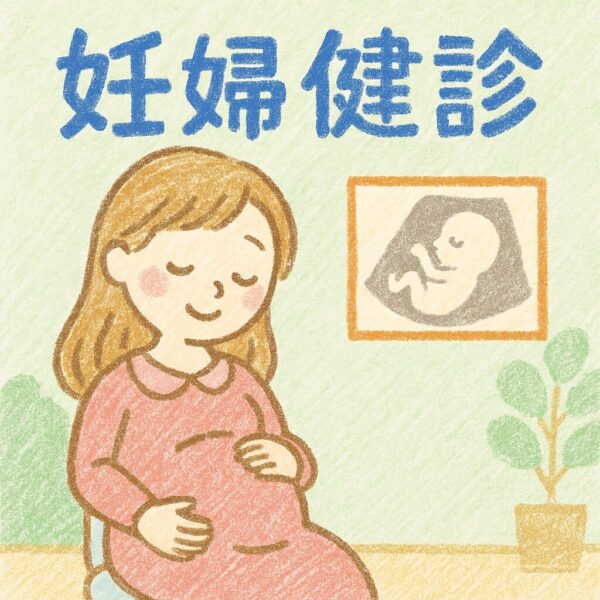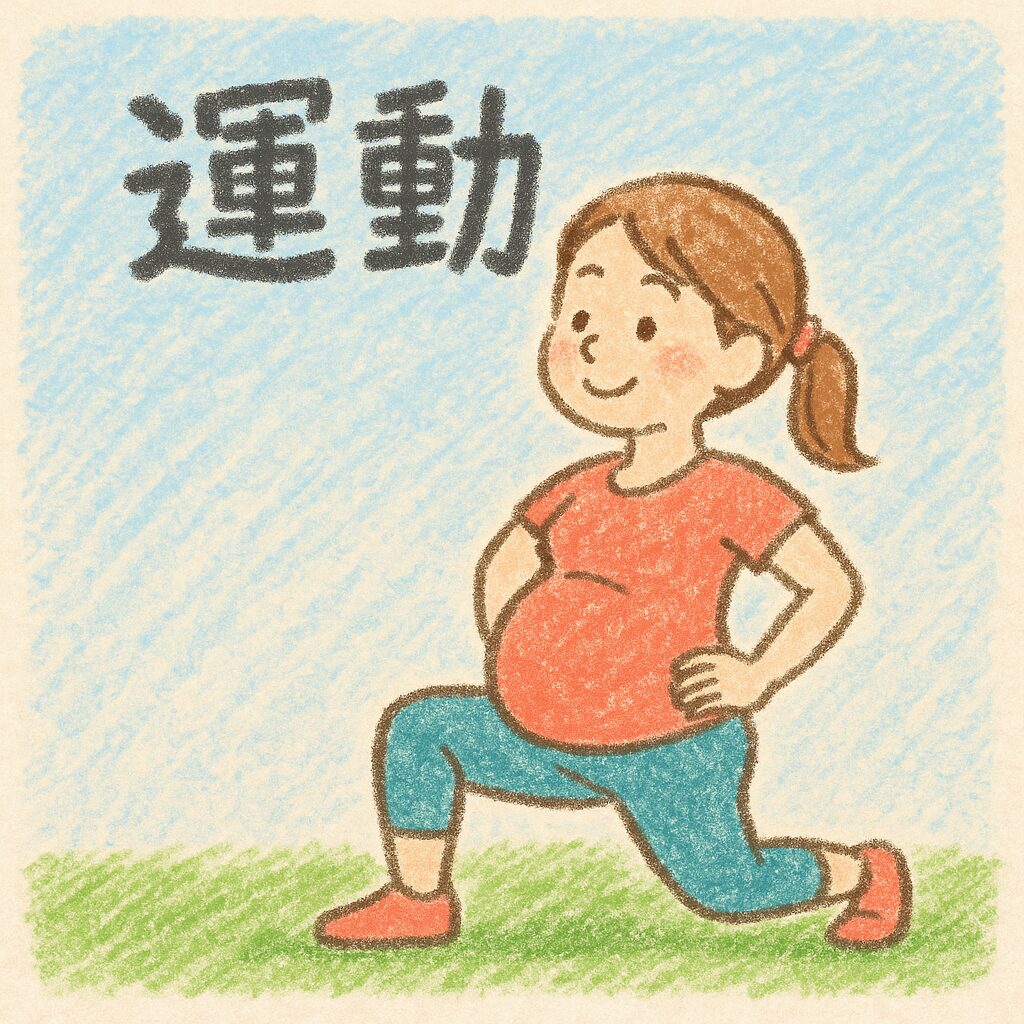妊娠がわかると、まず手にするのが「母子健康手帳」とその中に綴じられている妊婦健診の補助券(受診票)です。でも、

これってどう使うの?



いつでも使えるの?
と初めての妊婦さんにとってはわからないことばかり。
実はこの補助券、妊婦健診にかかる費用の一部を自治体が助成してくれる、とってもありがたい制度なんです。本記事では、補助券の使い方や注意点、受診の流れをわかりやすくご紹介。安心して健診を受けられるよう、準備しておきたいポイントもまとめています。
初めての妊婦健診、迷わずスムーズに進めましょう!
妊婦健診の補助券って何?
補助券の正式名称と配布時期
妊婦健診の補助券は、自治体によって「妊婦健康診査受診票」や「妊婦健診受診券」などと呼ばれています。
補助券は妊娠中に必要な健診費用の一部を公費で負担してくれるもので、妊婦さんにとって心強いサポートになります。
多くの自治体では妊娠11週までに届出を行えばスムーズに受け取ることができますが、遅れた場合も受け取れることがほとんどなので安心してください。初めての妊娠で不安な方も、まずは市区町村の保健センターに相談して、補助券の詳細や使い方を確認することが大切です。
使える健診内容と回数
補助券は主に妊婦健診の基本的な検査に使われ、尿検査・血圧測定・体重測定・胎児の心拍確認・エコー検査などに対応しています。
自治体によって若干異なりますが、多くの場合、14回程度の健診に使えるよう設定されています。
初期には2〜4週間ごとの健診、中期以降は週1ペースに増えていくため、受診券の回数にも理由があります。
補助券には「何週目の健診に使用するか」「どの内容が含まれているか」が記載されていることが多く、健診前に確認しておくと安心です。足りなくなった場合や転居した際は、再発行や交換が可能なケースもあるので、気になる場合は早めに役所に相談しましょう。
費用がどのくらいカバーされるの?
妊婦健診の補助券は、全額無料になるわけではなく「一部助成」という形が一般的です。
自治体ごとに助成金額は異なりますが、1回あたり5,000円~10,000円程度が補助されることが多いです。
例えば、エコー検査や血液検査など、内容によっては実費がかかることもあります。
特に初期の血液検査や後期の詳しいエコーでは、自己負担が出やすいので事前に確認しておくと安心です。
補助券を使っても支払いが発生する場合があるため、健診当日は保険証とともに、現金やキャッシュレス決済の用意もしておくとスムーズです。
自治体によって何が違うの?
妊婦健診の補助券は全国共通ではなく、自治体ごとに枚数や助成内容が異なります。
例えば、ある市では14回分の補助があっても、隣の市では10回分しかない、ということも。
さらに、補助金額や対象となる検査項目にも差があります。また、一部の自治体では妊婦健診以外にも、産後のケアやパパママ教室の受講に使えるクーポンが含まれていることも。
引っ越しなどで住民票の移動があった場合、再発行の手続きが必要になるため、早めに保健センターなどに確認しておきましょう。
地元の制度をしっかり把握して、上手に活用することが大切です。
補助券はいつどこでもらえる?
母子手帳と一緒にもらえるのが一般的
妊娠が分かり、産婦人科で「妊娠届出書」をもらったら、それを持って市区町村の役所や保健センターに提出します。
このタイミングで母子手帳と一緒に補助券が交付されるのが一般的な流れです。
妊娠が確定してからなるべく早く手続きを済ませることで、初期の健診から補助を受けられるようになります。
母子手帳と補助券は、今後の妊婦生活で何度も使う大事なアイテムなので、丁寧に保管しておきましょう。
受け取りに必要なものとは?
補助券を受け取るには、基本的に「妊娠届出書」「本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証など)」が必要です。
自治体によっては、産婦人科で発行された妊娠証明書の提出が求められることもあります。
また、代理人が手続きする場合には委任状が必要になることもあるため、事前に自治体のホームページや窓口で確認しておくと安心です。手続き自体は10〜15分ほどで終わることが多いので、時間に余裕のあるときに済ませておくのがおすすめです。
もらい忘れた場合の対処法
もし妊婦健診補助券をもらい忘れてしまっても、焦らなくて大丈夫です。
まずは住んでいる自治体の保健センターや市区町村の窓口に連絡しましょう。
事情を伝えると、必要書類を再確認のうえ再発行や郵送対応をしてくれるケースもあります。
また、補助券を使わずに健診を受けてしまった場合でも、領収書があれば一部の費用が還付される可能性があります。
受診時の領収書は必ず保管しておくと安心です。早めの相談が解決のカギになりますよ。


補助券の使い方と注意点
健診時に提出するタイミングは?



補助券は妊婦健診の受付時に提出するのが一般的のようですが、私の場合は診察時に看護婦さんにお渡ししていました。
初診時にはまだ使えないこともあるため、事前に病院へ確認しておくと安心です。
提出を忘れると補助が適用されず全額自己負担になる可能性もあるため、母子健康手帳と一緒に持ち歩くのがおすすめ。病院によっては提出のタイミングや方法に違いがあるので、初回にしっかりと説明を聞いておくとスムーズに活用できます。
毎回の健診前に券の枚数と内容をチェックしておきましょう。
有効期限や紛失時の対応方法
妊婦健診補助券には有効期限があり、原則として妊娠中の決められた期間内しか使えません。出産後は使えなくなるため、スケジュール管理が重要です。
また、紛失してしまった場合は速やかに市区町村の窓口へ連絡しましょう。
本人確認ができれば再発行してもらえることが多いです。万が一に備えて、補助券は大切に保管し、念のため写真で記録を残しておくのも良いアイデアです。
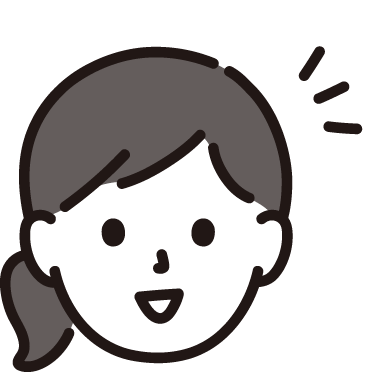
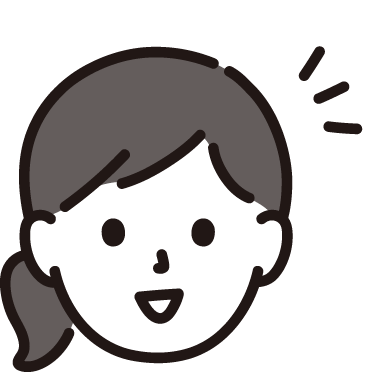
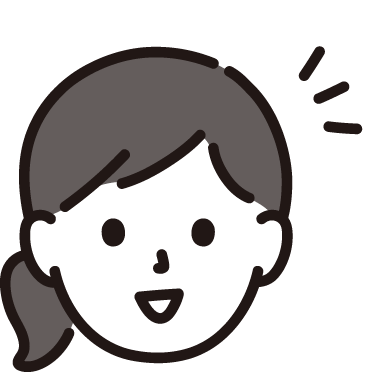
おすすめの管理方法は、クリアファイルに入れておいたり、検診用のバッグに入れておくことです。
また、妊婦検診用のバックはA4サイズの書類が入り、500㎖のペットボトルが入るA4サイズがおすすめ。検診の待ち時間が長いと、喉が渇いて飲み物がほしくなったりしてしまいます。
そして、妊婦検診中にはよく病院でアンケートをもらうことが多いので、一緒にクリアファイルに入れておくと次回の提出時に忘れずにおすすめです。小分けされているクリアファイルだと、書類を分けてわかりやすく管理できるので、より便利でおすすめですよ。
病院によっては使えないケースも?
すべての医療機関で補助券が使えるわけではありません。
補助券の使用は自治体と提携している病院に限られるため、事前に利用予定の医療機関が対象か確認が必要です。
特に里帰り出産などで他県に通院する場合は注意が必要で、補助券が使えないケースや一部自己負担になることも。
必要に応じて償還払い制度を利用できる場合もあるので、自治体の案内をよく読んで対応しましょう。
健診で補助券が使える内容とは
妊婦健診でカバーされる検査項目
補助券を使うと、妊婦健診で行われる基本的な診察や検査の費用を一部または全額カバーしてもらえます。
一般的には血圧測定、尿検査、超音波検査、体重測定、問診などが対象です。
妊娠週数に応じて必要な検査があり、妊娠初期の血液検査や貧血検査も含まれることがあります。
検査内容は自治体ごとに多少の違いがあるため、配布される案内資料をしっかりチェックすることが大切です。
自己負担になる場合がある費用とは
補助券でカバーされる範囲外の検査や処置については、自己負担になる場合があります。
たとえば、4Dエコーや胎児ドック、妊娠とは直接関係ない検査などが該当します。
また、土日や時間外に受診した場合に追加料金がかかることも。
診察時に「これは補助券でカバーされますか?」と確認することで、思わぬ出費を防げます。
領収書はすべて保管しておくと、後で確認しやすいです。
補助券を上手に活用するコツ
妊娠初期からスケジュールを立てよう
補助券を無駄なく使うためには、妊娠初期のうちから健診スケジュールを立てておくことがポイントです。
妊婦健診はおおよそ4週に1回から始まり、妊娠後期には2週に1回、臨月には毎週の通院が必要になります。
補助券の回数と照らし合わせて計画を立てておけば、急な出費や券の使い残しを防げます。
通院予定の病院に相談して、計画的に健診を進めていきましょう。


病院選びで確認すべきポイント
病院によっては補助券の取り扱いに差があるため、産婦人科を選ぶ際には「補助券が使えるか」「どの検査が対象か」をしっかり確認しましょう。
また、里帰り出産を予定している場合は、両方の病院で補助券が使えるか事前に問い合わせておくとスムーズです。
公式サイトや口コミ、自治体の案内を参考にすると安心して病院選びができますよ。
補助券以外にも使える助成制度をチェック
妊婦健診の補助券以外にも、自治体によっては妊娠・出産に関する様々な助成制度があります。
たとえば、不妊治療費の助成や出産費用の助成、交通費の補助などがあることも。
また、所得制限がある制度もあるため、早めに情報収集しておくのがベストです。
役所や保健センターに相談すれば、自分が使える制度を詳しく教えてもらえますよ。
まとめ
妊婦健診の補助券は、妊娠中の健康を守るための大切なサポート。自治体から交付されるこの券を上手に使えば、経済的な負担を軽くしつつ、安心して定期的な健診を受けることができます。使うタイミングや提出のしかた、対象となる医療機関をあらかじめ確認しておくことで、健診当日もスムーズです。初めてで不安な方も、母子手帳と一緒に補助券を持ち歩いておくのがおすすめ。小さな疑問も解消して、心もからだも健やかなマタニティライフを送りましょう。



![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4ce1b744.738f9186.4ce1b745.7b904795/?me_id=1270903&item_id=11295708&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fr-kojima%2Fcabinet%2Fn0000000358%2F4901470228276_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47fd04c7.059c3d9d.47fd04c8.6efb5d72/?me_id=1249568&item_id=10405245&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Falphakids%2Fcabinet%2Fimage283%2Fnh12s2140748_1.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47579724.f4945ab4.47579725.64083c3d/?me_id=1221018&item_id=10121875&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbunbougu-shibuya%2Fcabinet%2F55%2Fs2133342.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47fd18cb.33778aa8.47fd18cc.7ed02901/?me_id=1304143&item_id=10002519&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fstyle-on-bag%2Fcabinet%2Fth%2Flz-7031_2410.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/47fd221a.c8d8ee91.47fd221b.1164f6d3/?me_id=1387591&item_id=10000061&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fmonopia%2Fcabinet%2Fds-17922%2Fdgray240805.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)