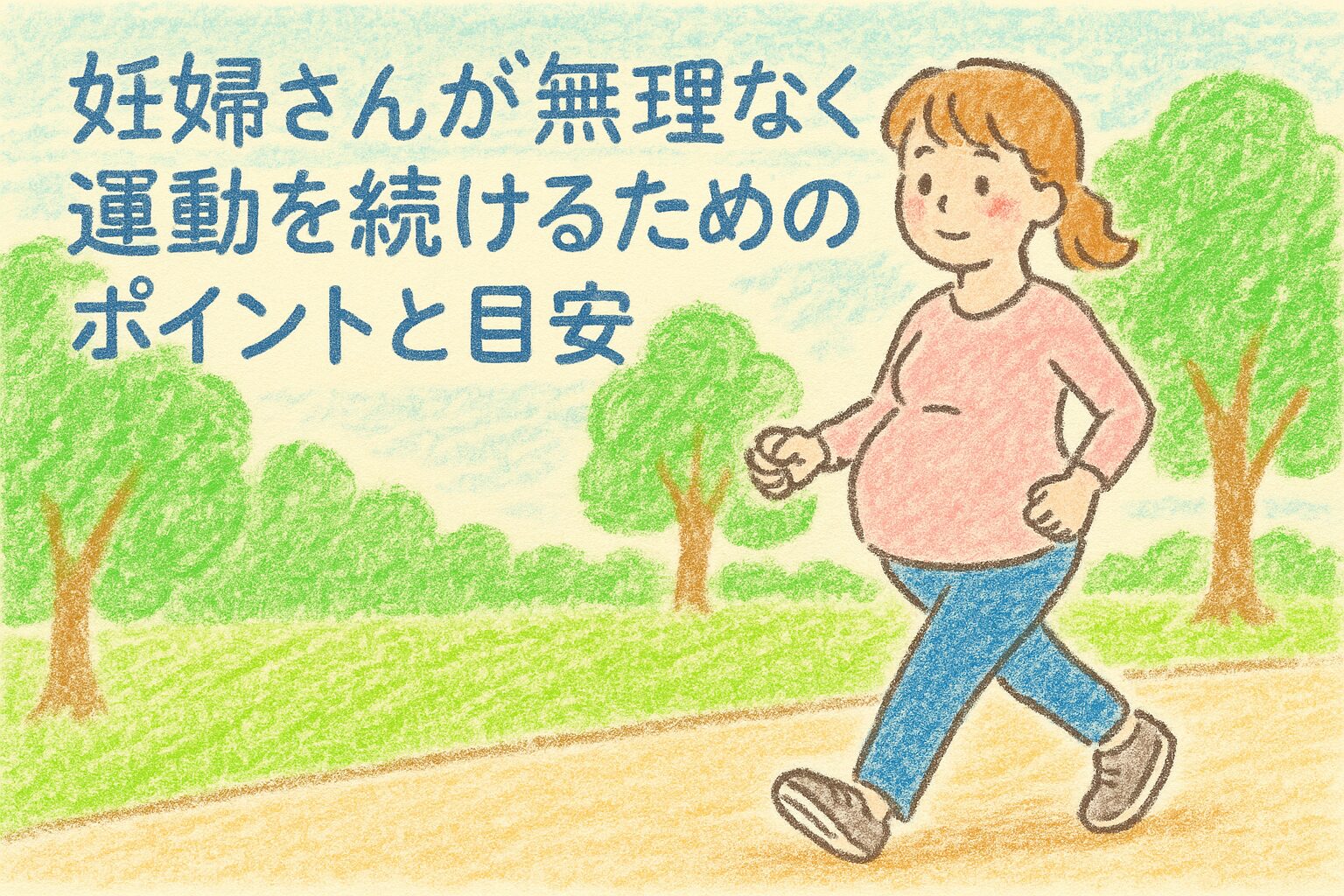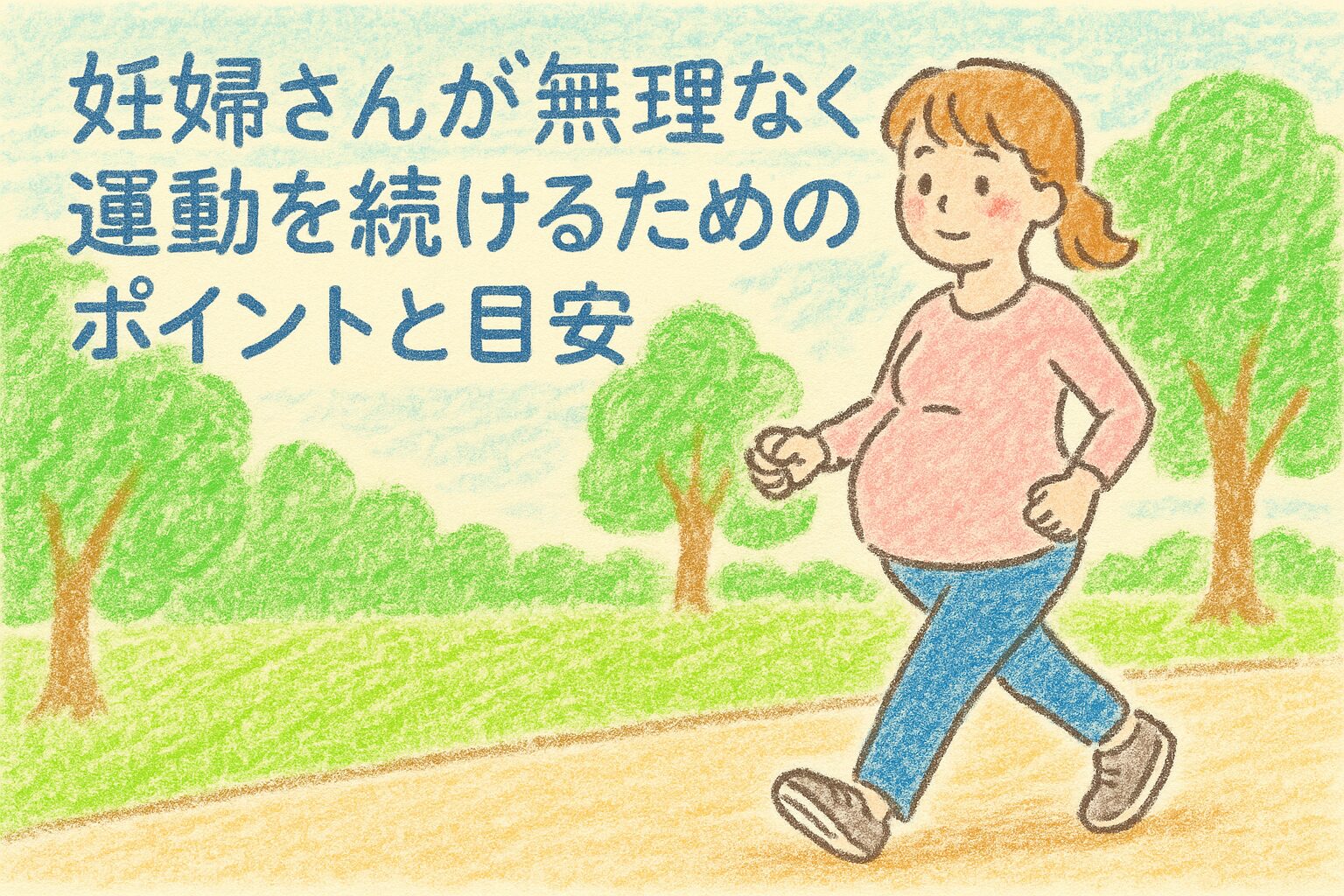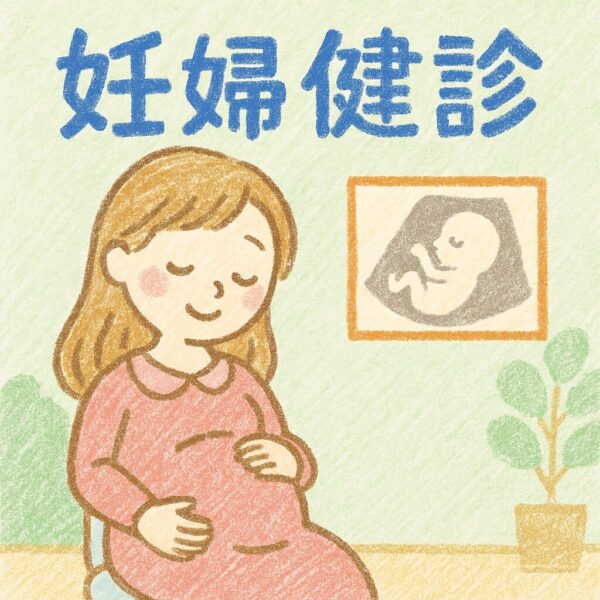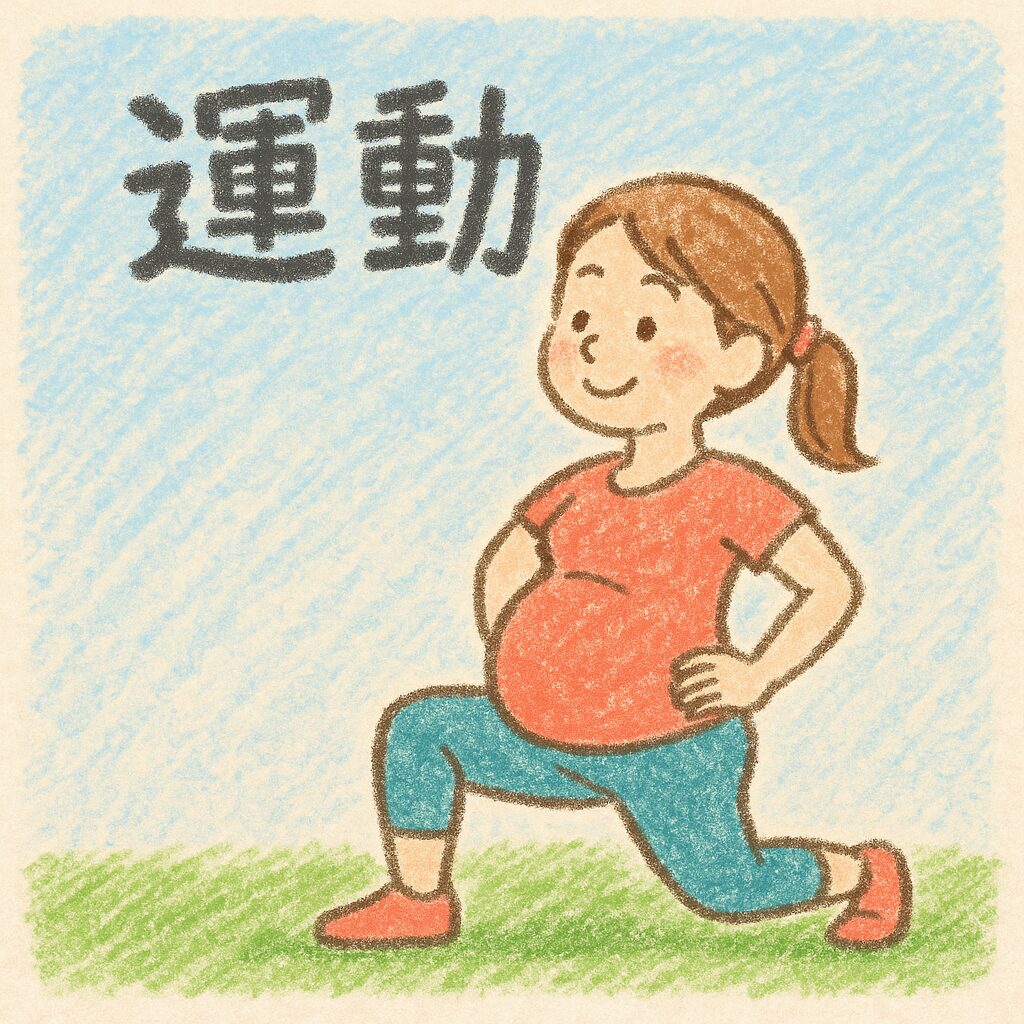妊娠中は赤ちゃんのためにも、自分の体調管理のためにも、毎日の「食べ物」がとても大切。
とはいえ、
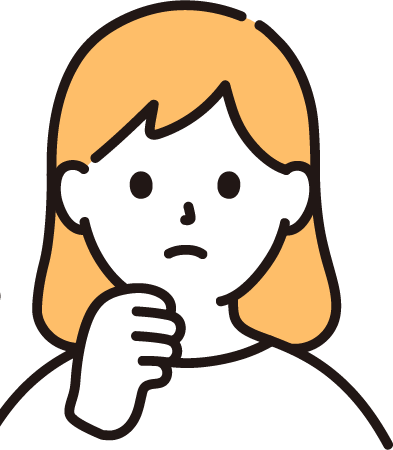
何をどれだけ食べればいいのか分からない…
という方も多いはず。
そこで今回は、妊婦さんの栄養管理をサポートしてくれる“アプリ”に注目!手軽に食事の記録ができたり、
必要な栄養素を確認できたりと、便利で心強い存在です。
この記事では、妊婦さんに人気の食べ物管理アプリや、使い方のコツ、選ぶときの注意点まで、分かりやすくご紹介します♪
これから検診に行く方へ。
補助券の準備と一緒に、無料でもらえるマタニティギフトのチェックは済みましたか?
\全員プレゼントなので忘れないうちに!/
妊婦の食生活を支えるアプリとは?
妊娠中に必要な栄養素とは?
妊娠中は、普段よりも多くの栄養素を必要とします。特に注目すべきなのは、葉酸・鉄分・カルシウム・たんぱく質・ビタミン類です。
葉酸は胎児の神経管の発達に、鉄分は妊婦の貧血予防に、カルシウムは赤ちゃんの骨や歯の形成に欠かせません。
これらの栄養素を毎日の食事でバランス良く摂ることが理想ですが、つわりや体調不良で思うように食べられないこともあります。
そこで、栄養素を見える化できるアプリが役立ちます。
自分が今、何をどのくらい摂取しているかがわかることで、不足しがちな栄養を意識でき、妊婦さん自身の安心にもつながります。
食事管理アプリの便利な機能
妊婦さん向けの食事管理アプリには、妊娠中に特化した便利な機能がたくさんあります。
たとえば、毎日の食事を記録するだけで自動的にカロリーや栄養バランスを分析してくれたり、摂りすぎ・不足している栄養素をアラートで教えてくれるものもあります。
また、妊娠週数に合わせて必要な栄養や注意点をアドバイスしてくれるアプリもあり、初心者でも安心して活用できます。
中には食材からレシピを提案してくれるものや、体調メモを付けられるものもあり、食事だけでなく日常の健康管理全体に役立ちます。
アプリで食事記録するメリット・デメリット
食事記録アプリの最大のメリットは、自分の食生活を「見える化」できること。
栄養バランスの偏りやカロリーオーバーに気づけるので、体重管理や栄養管理に役立ちます。
また、医師や助産師に相談する際にも、記録を見せることでスムーズに話ができるのも大きなポイントです。
一方で、毎日記録するのが面倒に感じたり、細かすぎる入力にストレスを感じる人もいます。
自分に合ったアプリを選び、無理なく続けることが大切です。「完璧に管理しなきゃ」と気負いすぎず、参考程度に使うというスタンスでも十分効果があります。
アプリ選びのポイントと注意点
安心して使えるアプリの選び方
妊婦さんがアプリを選ぶときは、まず「医療・栄養の監修があるか」をチェックしましょう。
信頼できる専門家が関わっているかどうかで、情報の正確さが大きく変わります。
さらに、使いやすさや見やすさも大事なポイント。
ストレスなく毎日使える設計かどうか、自分に合ったデザインや機能があるかを試してみるのも大切です。
また、口コミやレビューで他の妊婦さんの使用感を確認するのも◎。できれば無料で始められて、有料機能は後から検討できるアプリが安心です。
アプリに頼りすぎない意識も大切
便利なアプリも、すべてを任せっきりにするのは避けたいところ。
体調や気分はアプリでは測れない部分もあります。たとえば「今日はどうしても食欲がない」ときに、数字だけを見て焦って無理に食べてしまうと、かえってストレスになります。あくまでアプリはサポート役。「参考にする」くらいの気持ちで、最終的には自分の体の声を聞くことを大切にしましょう。
食事や記録が負担に感じるときは、少し休んでもOKです。
データの扱いに注意しよう
アプリには個人情報や体重、健康状態などのデリケートなデータを入力することが多くなります。
安心して使うためには、プライバシーポリシーや利用規約を確認し、情報の取り扱いが明確にされているアプリを選びましょう。
特にSNS連携や広告が多いものは、情報の共有範囲が広がる場合があるので注意が必要です。
できれば国内開発のアプリで、妊婦向けに特化しているものを使うとより安心です。自分の情報を守る意識も、これからママになる第一歩!
人気の妊婦向け食事管理アプリ5選
カロミルでカロリー&栄養チェック


出典:カロミル
「カロミル」は、食事を入力するだけで自動的にカロリーや主要栄養素を算出してくれる便利なアプリです。
写真を撮るだけで食材を判別する機能もあり、忙しい妊婦さんにもぴったり。
妊娠中は体重管理が重要になるため、日々のカロリーや糖質、脂質、たんぱく質のバランスを知っておくのはとても大切です。
「カロミル」では、摂取した栄養素がグラフで可視化されるので、不足しやすい鉄分やカルシウムも意識的に摂れるようになります。
さらに、体重や体調の記録もできるため、食事と健康管理を同時にサポートしてくれる万能アプリです。


あすけん妊婦モードの活用法
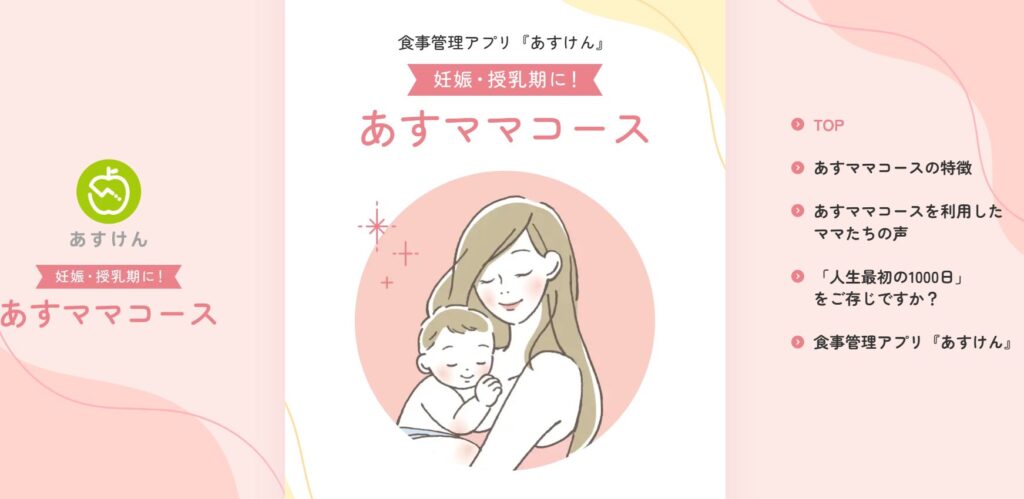
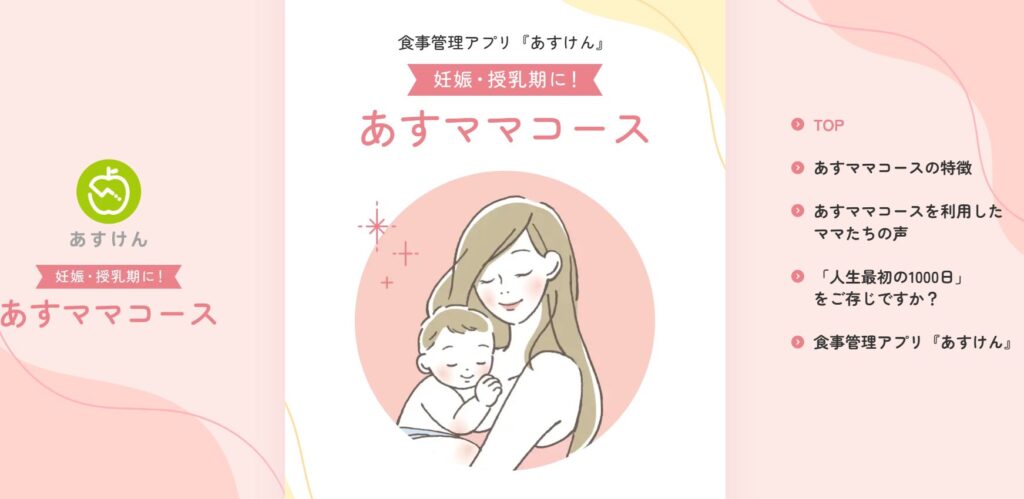
出典:あすけん
健康志向な人に人気の「あすけん」には、妊娠中でも活用できる食事管理モードがあります。
食事内容を記録すると、AIが栄養バランスを分析し、アドバイスをくれるのが大きな特徴。
妊婦さんの悩みに応じたコラムや健康情報も読めるので、食事だけでなく知識面でも頼れる存在です。
また、体重の推移をグラフで確認できたり、妊娠週数に応じたコメントが届くなど、モチベーション維持にもつながります。
つわりが辛い時期でも、「今日はこれだけ摂れた」と自信につながるようなサポートが魅力です。


Baby+:妊娠週数に応じたアドバイス機能


出典:Baby+
「Baby+」は妊娠・出産アプリとして人気ですが、実は食事に関するアドバイスも充実しています。
妊娠週数に応じて、その時期に必要な栄養素やおすすめの食材がわかりやすく紹介されるため、何を食べたら良いか迷いがちな妊婦さんにはとてもありがたい存在です。
また、妊娠経過に沿った成長のイラストやメモ機能もあり、妊娠生活全体を楽しく記録できます。
食事だけでなく、胎児の成長や自身の体調も一緒に見守っていけるので、トータルで使いたいアプリとしておすすめです。


妊婦さんにおすすめのレシピアプリ
栄養満点!DELISH KITCHENの使い方


出典:DELISH KITCHEN
「DELISH KITCHEN」は、栄養バランスの取れたレシピが豊富に揃っていて、妊婦さんにも大人気のレシピアプリです。
特に「栄養士監修」レシピや「鉄分・葉酸たっぷり」など目的別で検索できるのが魅力。
動画付きなので、料理が苦手な方でもわかりやすく、時短にもなります。
つわり中でも食べやすいあっさりメニューや、体重管理に配慮した低カロリーレシピも充実。
冷蔵庫にある食材からメニューを探せる機能もあり、買い物前に確認できるのも便利。毎日の献立に悩む妊婦さんの強い味方です。


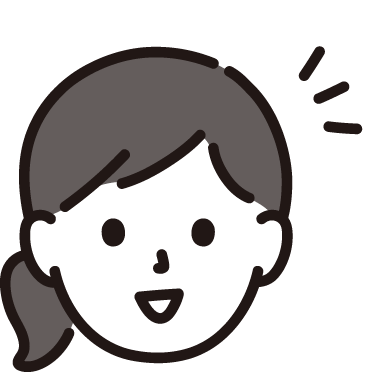
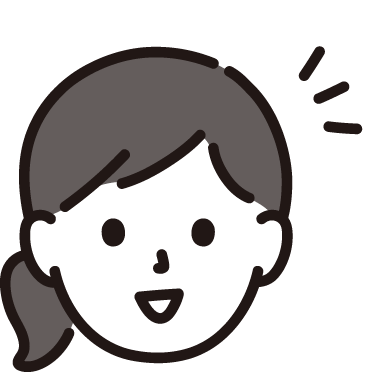
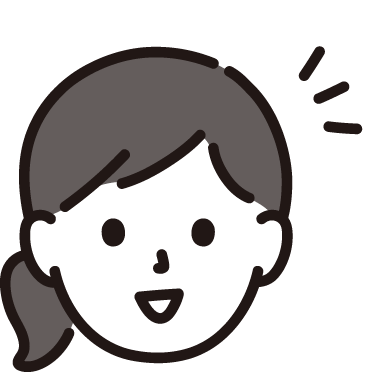
私はDELISH KITCHENで動画を見ながら料理をしていました。
妊娠中も使っていましたが、普段使いでもおすすめなので、
ママになってからも使っています♪
また忙しい妊婦さんには「DELISH KITCHEN」プロデュースの宅配弁当もおすすめ!
ストレスを溜めずぎずに過ごすためにも、是非取り入れてみてくださいね♪
\今なら初回限定¥2,000 OFFキャンペーン中/
Kurashiruで優しい和食レシピを検索
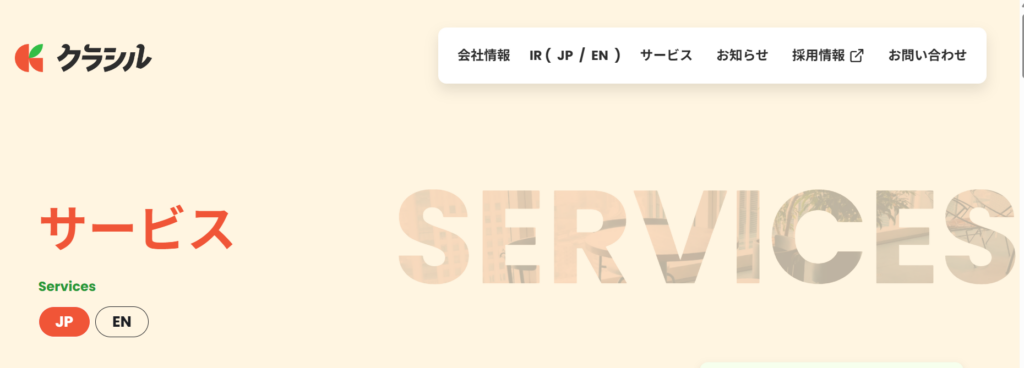
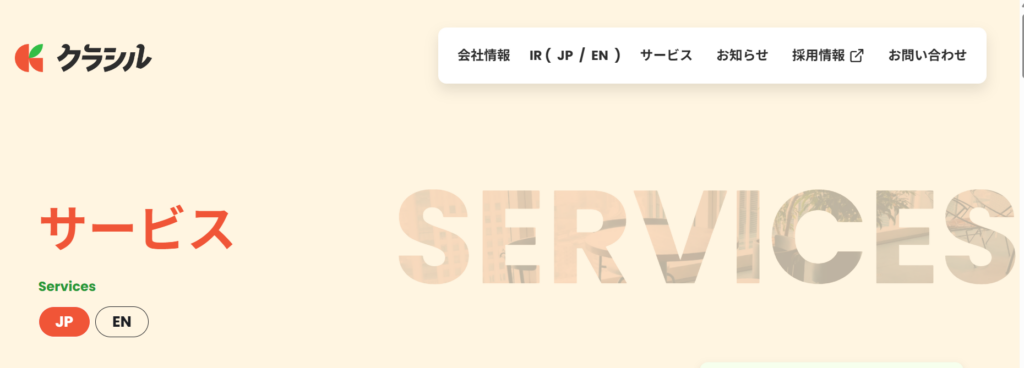
出典:クラシル
「Kurashiru(クラシル)」は、簡単で美味しい家庭料理のレシピが満載の人気アプリ。
特に妊婦さんに嬉しいのが、和食系のメニューが多い点です。和食は脂質が控えめで、野菜や魚もたっぷり使えるので、妊娠中の体に優しく、栄養も摂りやすいです。アプリ内では「妊婦」「鉄分」「葉酸」などのキーワードで検索が可能。
毎日の食事に役立つだけでなく、旬の食材を使ったレシピも多く、栄養の偏りも防げます。
見た目もきれいで、作っていて楽しくなる工夫もいっぱいです。


mamariで先輩ママのリアルレシピを参考に


出典:mamari
「mamari(ママリ)」は、妊娠・出産・育児に特化した情報共有アプリで、ユーザー同士の体験談やレシピもシェアされています。
特に妊娠中の「何を食べていた?」というリアルな投稿は参考になることが多く、自分の状況に似た人の体験を見つけやすいです。
「つわりの時でも食べられたもの」「便秘解消レシピ」「体重管理のために工夫したこと」など、実際の妊婦さんの声がそのまま反映されているのが特徴。
専門家のアドバイスではなく「現場の声」が聞ける点が大きな魅力です。


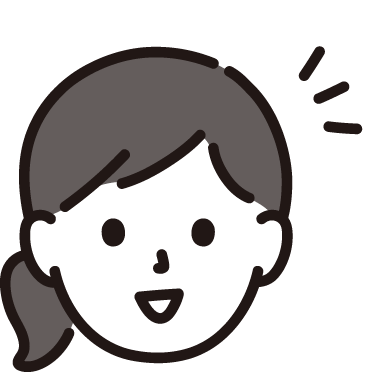
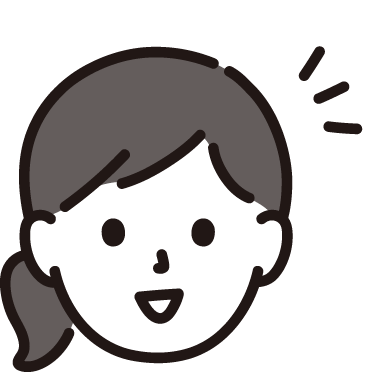
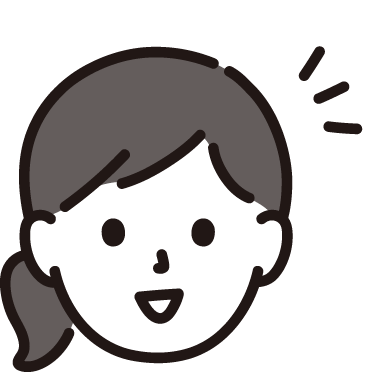
mamariはいろんな実体験が漫画で読めたり、豊富な話題の記事が多くて面白いのでよく見ていました。自分の妊娠週数の体調の変化などの記事はとても参考になりました!
アプリで楽しく栄養管理を続けるコツ
無理なく毎日記録するための工夫
アプリでの栄養管理を続けるには、完璧を目指さず「ゆるく続ける」ことが大切です。最初は1日1回、食事の写真だけ撮って記録するだけでもOK。忙しい日は夕食だけ、週末はまとめて記録でも大丈夫です。
あらかじめよく食べるメニューを登録しておけば、入力の手間も省けます。
大切なのは「続けること」なので、完璧主義にならず、楽しみながら使える工夫をしましょう。自分なりのペースで続けていけば、いつの間にか体の変化や習慣もついてくるはずです。
グラフ機能でモチベーションUP
多くのアプリには、体重や栄養バランスの推移をグラフで見られる機能があります。数字や視覚的な変化は、小さな達成感につながり、続ける原動力になります。たとえば、「鉄分が増えた週」や「体重が理想ラインに収まった日」を確認すると、自然と自信がついてくるもの。
週単位や月単位での振り返りを習慣にするのもおすすめです。妊娠中はちょっとした変化に敏感になる時期なので、グラフという“見える化”をうまく活用しましょう。
ごほうびルールで楽しく継続
毎日記録できたら小さなご褒美を設定するのも、継続のコツです。たとえば「1週間記録が続いたら、好きなスイーツを1つだけOKにする」など、楽しみを組み込むことでモチベーションを保てます。
妊娠中は制限が多くてストレスを感じがちなので、アプリでの記録がポジティブな体験になるような工夫をすることが大切。自分へのねぎらいとして、お気に入りのマタニティグッズを買ったり、癒しグッズを取り入れるのもいいですね。楽しく、ゆるく、がキーワードです!
まとめ
妊娠中は体も心も変化が多く、不安になることもありますよね。
そんなとき、食べ物を楽しく記録しながら安心して過ごせる「アプリ」は、ママにとって頼れる味方。
今回ご紹介したポイントを参考に、自分に合ったアプリを選び、無理なく続けられるスタイルを見つけてみてください。大切なのは、数字だけにとらわれすぎず、体の声をしっかり聞いてあげること。
あなたの毎日のごはんがより素敵なものになりますように♪
そして、最後に頑張っているプレママさんへ嬉しいお知らせ。
今、お金の相談ができる『ベビープラネット』で無料相談をすると、可愛いおむつポーチや育児グッズが必ずもらえるキャンペーンを実施中です。 相談はオンラインOKなので、体調が良い日にサクッと『お金の健康診断』も済ませて、豪華特典をゲットしちゃいましょう!
\【無料】選べるプレゼント付き!保険の相談予約はこちら/